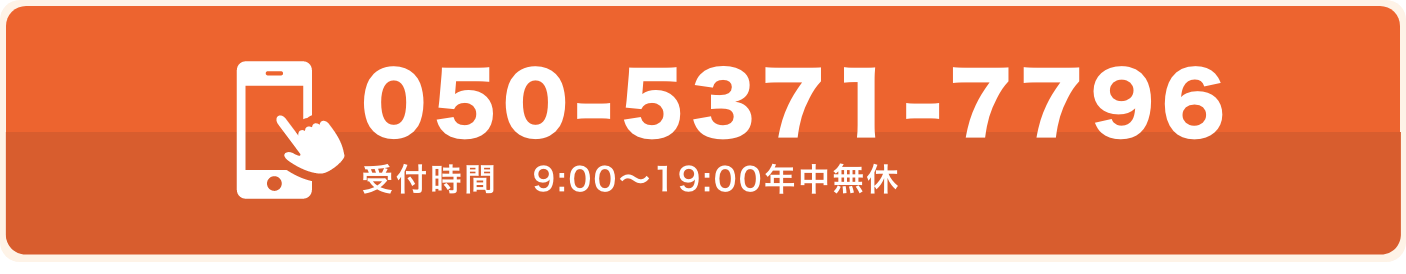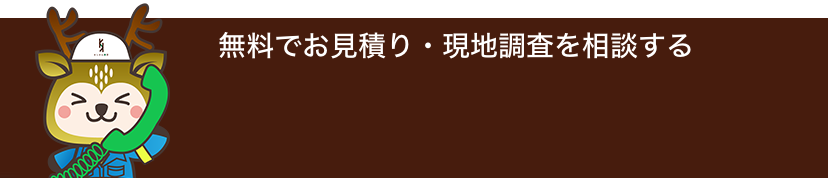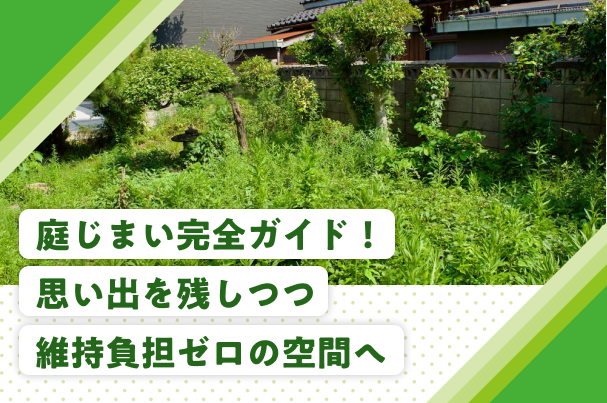
はじめに―庭じまいが必要とされる背景
日本の住環境やライフスタイルはこの十数年で大きく変わりました。共働き世帯の増加や高齢化が進むなかで、草木の手入れを「癒やし」と感じていた庭が、いつの間にか「重荷」へと変わってしまうケースが目立ちます。芝生の刈り込みや枝の剪定、雑草の除去――こうした作業を自力で続けるには体力・時間・費用の三つが必要ですが、年齢を重ねるほどハードルは高くなる一方です。
そこで注目されるのが庭じまい。これは長年愛着を持って世話してきた庭を丁寧に整理し、縮小あるいは撤去して、新しい暮らしに合った空間へ再生するプロセスを指します。単なる伐採や解体ではなく、「思い出を未来につなぐリセット作業」と捉えることが大切です。
庭じまいを決意する三つの主な理由
-
維持管理の負担が限界を迎えた
高齢になると脚立を使った高木の剪定は転落事故のリスクが高まり、夏場の草取りは熱中症を招きかねません。業者に依頼すれば安全ですが、毎年の費用が家計を圧迫します。 -
住環境や家族構成の変化
子どもが独立して庭で遊ぶ機会がなくなる、転勤や介護で空き家になる――こうした状況では雑草が伸び放題となり、隣家へ迷惑をかける恐れがあります。 -
庭を別の用途へ転換したい
最近は「駐車場を拡張したい」「手間の少ない家庭菜園を作りたい」「雑草対策として防草シートと砂利で覆いたい」といったニーズが急増中。庭じまいはライフスタイルの再設計とも言えます。
庭じまいの基本ステップ
1. 現状とゴールを可視化する計画フェーズ
まずは樹木の本数・樹高・庭石や灯籠などの重量物・ウッドデッキやフェンスなどの構造物を一覧化します。残すものと処分するものを家族で話し合い、将来の使い方をスケッチに落とし込みましょう。
2. 伐採・抜根・撤去の実働フェーズ
-
樹木の伐採・抜根:幹径20センチ未満の低木はDIYが可能ですが、高木や根が深い木は専門業者へ。地下に根が残ると配管や基礎に悪影響を与えるため、駐車場や建物下になる部分は完全抜根が基本です。
-
庭石・灯籠の搬出:数百キロ級の石材はクレーンで吊り上げる必要があり、搬出ルートの確保と境界フェンスの養生が欠かせません。
-
ウッドデッキ・フェンスの解体:劣化した木材には釘やビスが残っています。安全第一で分別し、産廃として適正に処分します。
3. 再整備フェーズ
撤去完了後は、新しい用途に合わせて整地・転圧を行い、防草シート+砂利、コンクリート舗装、透水性ブロック、人工芝、菜園用花壇などを設置します。3Dパースや簡易イメージ図を作成し、家族全員で完成像を共有すると失敗が減ります。
費用と期間の目安
都市近郊の戸建て(敷地50坪・庭20坪)で、
-
中高木4本の伐採+抜根
-
庭石3基の搬出
-
ウッドデッキ8㎡の解体
-
防草シート+白砂利20㎡施工
といった内容を専門業者に依頼した場合、総額は40万~60万円、作業期間は3~7日が一般的です。高木が10メートルを超える、庭石が極端に大きい、隣接道路が狭くクレーンが入らない――など条件が厳しい場合は、追加費用や日数が発生する点に留意してください。
業者選定で必ず確認したい五つの項目
-
庭じまいの施工実績と直近の写真付き事例を提示できるか
-
伐採・撤去物のリサイクルや産業廃棄物処分ルートが明確か
-
近隣への事前あいさつ・騒音粉じん対策の計画書を用意しているか
-
地中障害物(古い基礎や配管)発見時の追加費用条件を明記しているか
-
解体後の地盤沈下や残根発芽に対する保証期間が設定されているか
複数社から詳細見積もりを取り、項目ごとに比較すると費用と安全性のバランスが見えやすくなります。
庭じまい後の活用アイデア
-
駐車スペース拡張:コンクリート舗装に透水性ジョイントを組み合わせ、雨水浸透とヒートアイランド抑制を両立。
-
家庭菜園+コンポスト:レイズドベッドを配置し、堆肥づくりまで一体化すればエコで健康的。
-
ドッグランや子どもの遊び場:人工芝とウッドチップを併用し、転倒時の衝撃を緩和。
-
メンテナンスフリーの景観:防草シートの上に伊勢砂利や溶岩石を敷き、シンボルツリーを一点配置して四季の変化を楽しむ。
まとめ――思い出と未来をつなぐ庭じまい
庭じまいは「もう庭を維持できないから仕方なく片づける」後ろ向きな作業ではありません。むしろ、家族の記憶が詰まった空間を次のライフステージに合わせてアップデートし、暮らしをより快適にする前向きなリノベーションです。維持費や体力的負担を減らしつつ、駐車場・菜園・趣味のスペースなど新たな価値を生み出すためにも、早めに計画を立て、信頼できる専門業者と二人三脚で進めることを強くおすすめします。